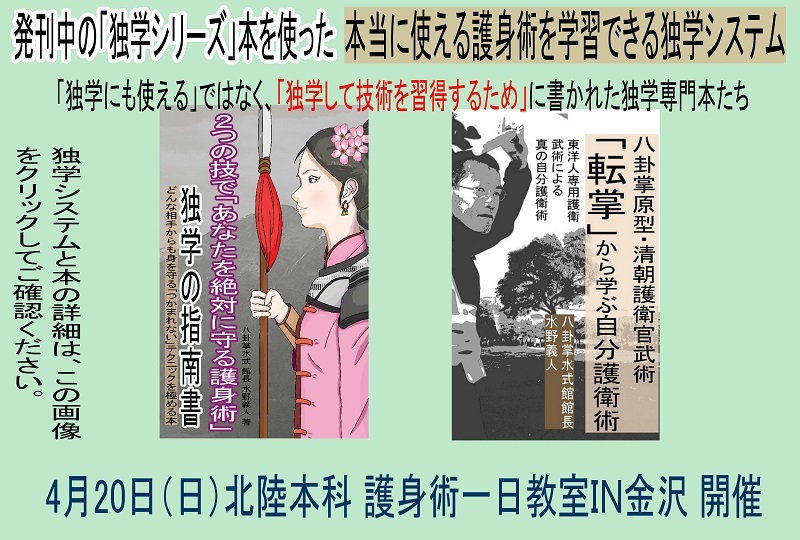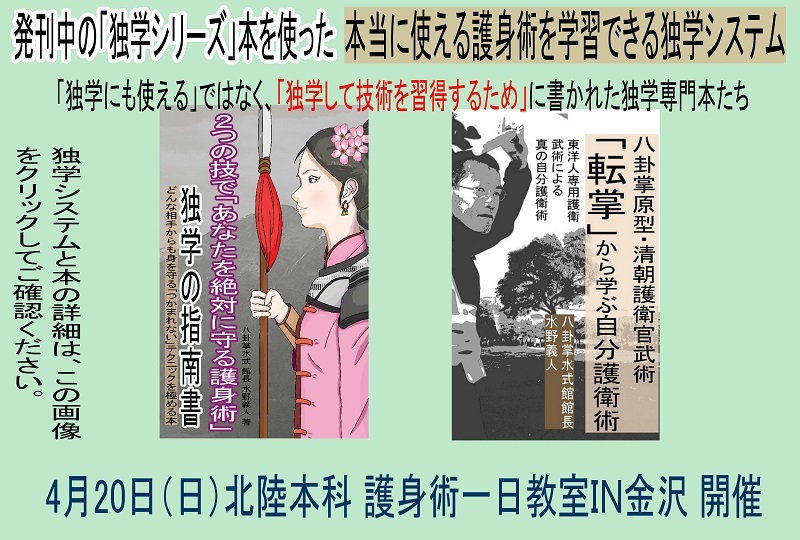私が言った、「良師三年」。これはとても深いのである。しかし説明ができないのである。
日本の武術愛好家の多くが言っている、良師三年とは、全く違うのである。多くの愛好家の言う、「良師三年」が真実なのか、それはここでは触れない。どうでもいいからである。真偽など、人の経験にもよるものだ。
私は、楊師より学んだ技術体系を指導する師を求めて、多くの道場を見た。探した経験があるのである。自分一人で、楊師より授かった技法を、確立する自信が無かったからだ。その意欲は、一番弟子に教え始めるようになってから、強くなった。
「人に教えるなら、私自身が、その拳理を最も知っていなければならぬ。」
拳理を外に求めていた。習ったものは習ったもの。習ったものの発展のためには、新たな師に就く必要があると、一つの指導を受ける際の「形」に囚われていたのである。
しかし転掌の技法を伝える師は、国内にも国外にも居なかった。楊師の足取りも不明であった。私は絶望に近い感覚を覚えていた。私に学ぶ者もいるのに、私がその道を示すことができない。その暗闇の中で、義務感から、ただ練習の場に立ち続けた。
「ただ惰性で行うだけではだめだ」
私は、自身の経験から、この意見に賛同できない。なぜなら、私が、行き詰まりの中で気づいたのは、惰性で立ち続けた中で起こったからである。
ただ、こなすだけ。決められた練習を、ただ行うだけ。Youtubeの広告主に言わせたら、まったくけしからん練習姿勢であろう。しかし私は、この練習に取り組む姿勢こそ、多くの何かをもたらす、より大きなものからの暗示に触れる、プロセスであると、何度も経験するうちに確信してしまったのだ。
最初は、偶然だと思っていた。なぜならそれら(直感・インスピレーション)は、何の規則性もなく、突然来るからである。ある時は、警備の仕事を終える瞬間にやってきた。公園は真っ暗である。しかし私は、そこで思いついたことを試したくて、深夜0時を回っても単換掌をし続けた。斜め後方スライドに関わる重大な内容であった。突き動かされるような感情が抑えられず、家に帰ってもそれをし続けた。
その時の直感は、私の単換掌理を、より高次の安心をもたらすものに引き上げた。それ以後、練習の中で思いつくことは、なんでも試したのである。しかし面白いことに、自分が「こうではないか?」と思って取り組むと、その取り組むものとは違った、以前よくわからなかった課題に関わることについて、思いつくのである。
自分が改善を望むところに取り組んでいるところと、見えにくい箇所でつながっている部分に、光が当たったのだろうと思う。当時の自分の思考では、そのつながりが見えなかったから、「思いがけないところがわかった」と感じたのだろう。
私は、自分の内からくる自分の直感でありながら、その直感のプロセスをコントロールすることができないことに、言いようのない無力感を感じていた。直感を自分の管理下に置こうとしたのである。しかし、それは全く私の意図に従う気配がない。しかし、必要な時にやって来るのである。
「必要と感じる=自分がその問題を克服することが可能なレベルまで自然と上がっている→そのレベルで模索することで、必要な直感が自然とやって来る」
そういうことであると、私は納得した。この深く落ち込むような納得の状態に、追い打ちをかける心情の転機がやって来る。こんどの転機は、内面に対するものである。
筆頭門弟のルーツが、かほく市であった。私はその事実を知った時、気に留めていなかった。しかしルーツが宇ノ気小と知った時、そこから考えが根底から変わったのである。
私は学生の時、加賀の哲人・西田幾多郎先生の胸像画を見て、この人の、なにやらすっきりしない、笑顔になりきっていない薄ら笑みの表情に、自分と同じ空気を感じたのだ。この西田幾多郎先生こそが、宇ノ気小の先輩卒業生なのである。
高校の倫理の授業で、西田哲学の「純粋経験」を耳にした。しかし当時は、なんらの感情も抱かなかった。すでの楊師より、一通りのことを習った時期であったにもかかわらず。そして時は流れ、筆頭門弟を育て、その家のルーツが、かほく周辺にあったことを知り、かほくに関わるようになると、宇ノ気出身の西田幾多郎先生の話が再び出てくるのである。
私は、上記の「直感」のプロセスに、大きな悩みを感じていた。単なる自分の、思い付きではないか?いい加減なものではないか?確証もないものを、信頼していいものか?と。
そのタイミングで、西田先生の「純粋経験」を知ったのである。言葉で表すには、まったくもっておおきすぎる存在。その大きすぎる存在と、一緒になった時の経験。先生は、言葉に表すことができないその存在を、あえて言葉によって説明しようとして、大きな試みと苦闘をしておられた。
私は、この偉大な先人が、生涯をかけて思索し、向き合ったものに、触れていたのだ。自分の中で、すべてをささげて、進んできたものだったから、より大きなものが、必要なタイミングで、私に、私の思考などはるかに超えた部分で、直感をもたらした。
西田先生の「純粋経験」との出逢いは、よくわからなかった、老子の世界観や、インド哲学の「在る」の概念に、大きなヒントをもたらし、これらの思想のつながりを感じさせたのだ。
「良師三年」は、我が師より伝えらえた概念である。当時は、それを何気なく聞いていた。しかし良師が私とつながり、その師より、必要なタイミングで何度も教えを受ける中で、私は楊家転掌門に伝わる「良師三年」の概念を、深く確信することになったのだ。
楊家転掌八卦門には、そのシンプルな修行体系から、「成ること三年」の門伝があった。真摯に、素直に師に従って習練に励むなら、その体系の無駄の無さが、修行者を三年で旅立たせる、というもの。ゆえに、良師「三年」なのである。これは、楊家武術になってから生まれたものではない。古来より言われる「良師三年」とは、この意味であったと私は確信しているのだ。昔日の武術体系が、皆シンプルで即効性あるものばかりであったことが、確信する理由の一つである。
以前車で生活をすることを余儀なくされた時、一番弟子の娘と、練習後、あちこちの見晴らしのいい場所で、瞑想をしていた。彼女は瞑想の重要性を知り、私よりも先にそれを採り入れた天才である。彼女は、インド哲学の「在」の概念を体現したくて、その探求に熱心であったのだ。彼女は、見晴らしのいい、開けた場所で座って心を静める静寂の瞑想と、無心にあるがままに風景をスケッチし続ける動の瞑想を好んだ。私はこれまでずっと、彼女の瞑想に付き合う中で、私自身も、その方法を学んだ。
しかし一番弟子が最初に理解したのは、「在」の概念と本質的で同じである「老子」の世界観の方だった。彼女にとっては、「老子」のいう、よく見えぬ大きなものを感じるきっかけは、インド哲学であった。わたしは、西田哲学であった。
楊家門の開祖は、弟子たちに、技法のシンプルさの維持を厳命した。多くの型を作ることを善としなかった。八母掌・老八掌のような、套路(総合型)の形式は採らず、ただ主要転掌式という単式練習のみを構築しただけだった。そしてその主要転掌式に、武器術をすべて対応させた。「あっという間」に修行期間が終る技術体系を組んだのだ。
楊家門開祖が狙ったのは、短期習得・・・それは世俗的な理由である。より深い意味はこうだ。ヒントに留めることで、多くの修行者が、極力早く、自分で研究する段階(自分の直感による発展の段階)に移行することを狙ったからだ。これも門伝である。私は常々、私に続く、将来人を導き得る弟子に、そのことを言う。
「宇宙と一体となる」とは、このことを言っているのだ。宇宙とは、自分に直感を与える、私の中にある、そしてどこにもあり、すべてをつつみ、かつすべてである、説明のできない存在である。私はそれの存在のあることを理解した。しかし、その存在がどういうものであるかは、説明できないのだ。それは直感を私にもたらすものであるのだが、私の道徳とか、信念とか、善悪の判断基準なんかを、はるかに超えた概念で私に何かをもたらす。だから、コントロール下になんか置くこともできない。知ることもできない。ただそこに「在る」ということを理解するだけである。
私の希望なんか、吹き飛ぶかのような流れを、何度も経験した。修行の過程のなかで、大切な宇宙を4つも失った。私はその4人との永遠の別れを「必要なプロセス」などと認めたくなかった。それで長い時間、苦悩した。
きっとその4つの宇宙とは、永遠の別れをし合う相関関係の中で、互いの人生の中に「在る」ことを位置づけられたのだろう。今度はきっと、私自身がこの世界から「退場」することで、私の後に残る者は、何かがきっかけとして発動されたり、何かが始まるはずである。私の場合もそうであったように。
私は今後、技法の伝承と共に、達人に至るまでのプロセスを、詳しく説いていくことを考えている。技法の執筆と、達人になるうえでの直感の共有を、目指すために。それについて、動画でも詳しく述べていきたい。楽しみにしていてほしい。