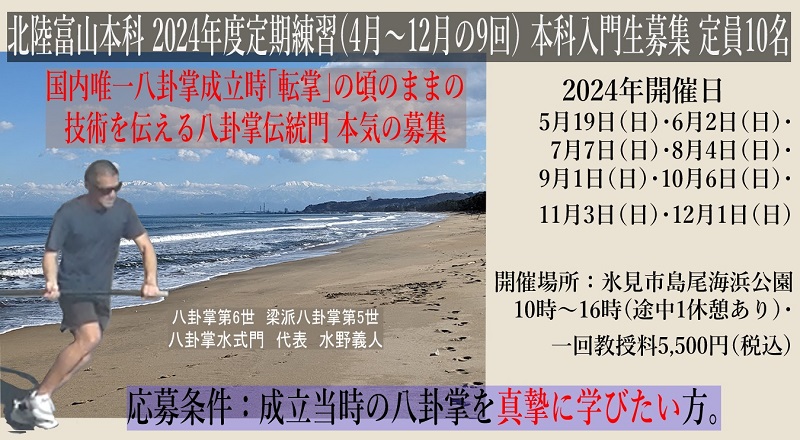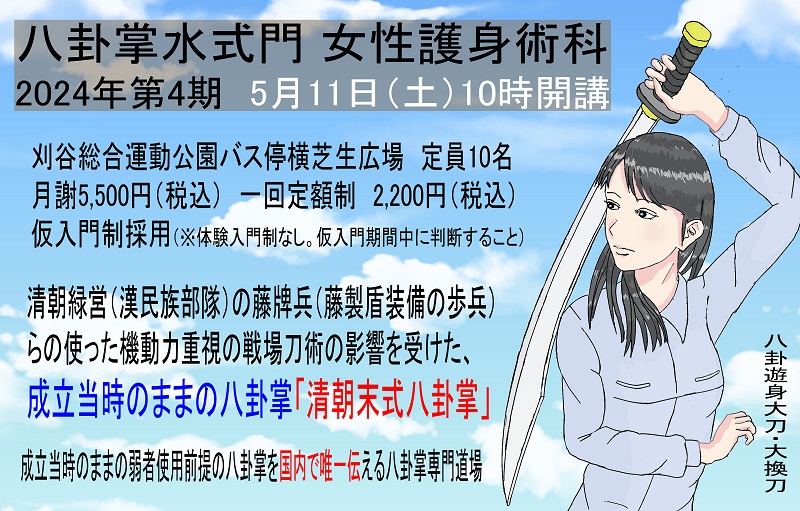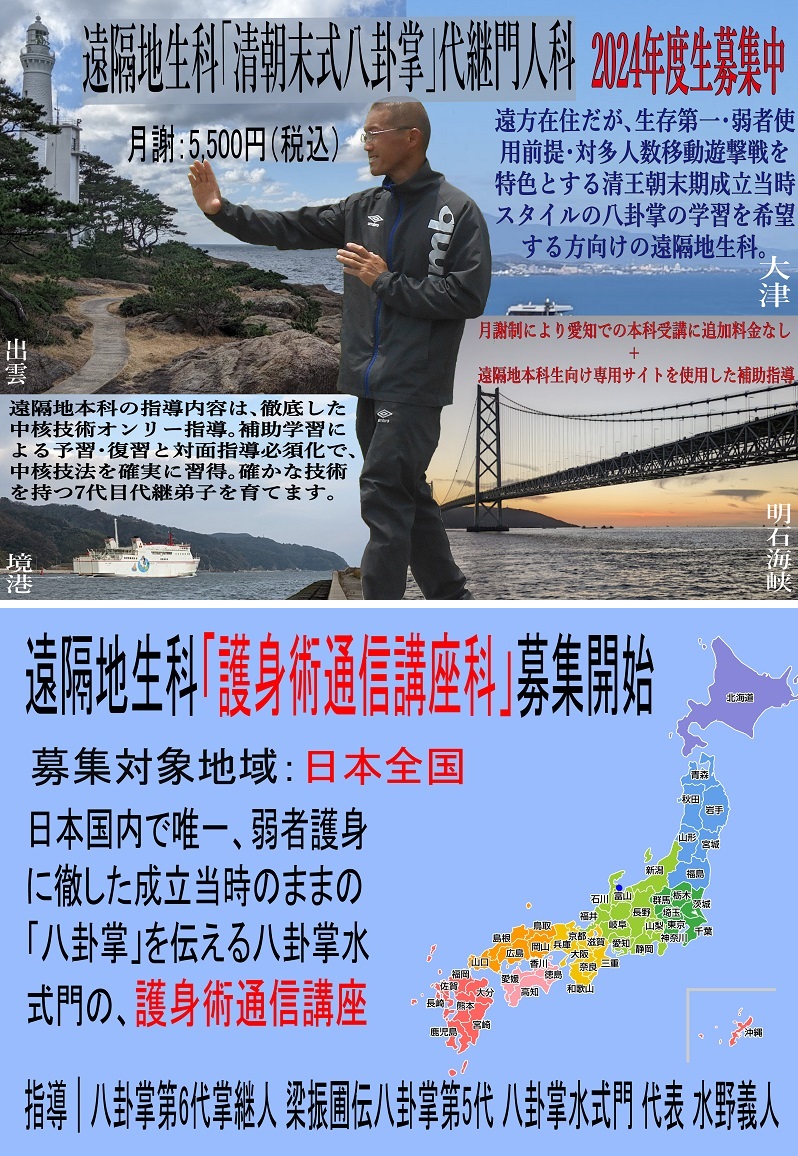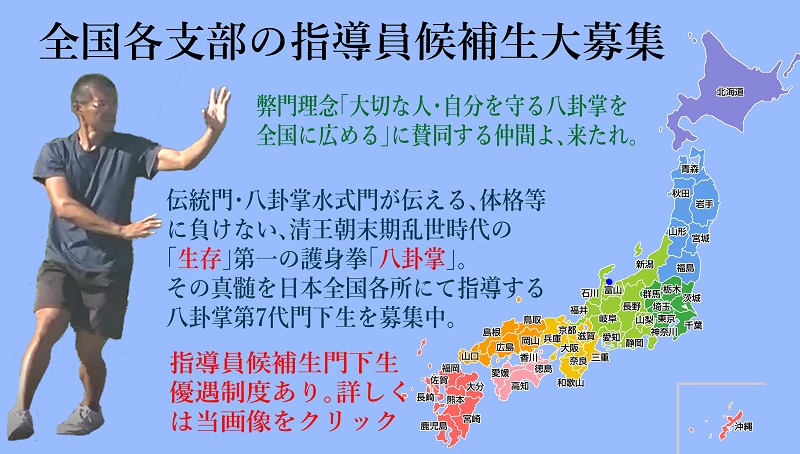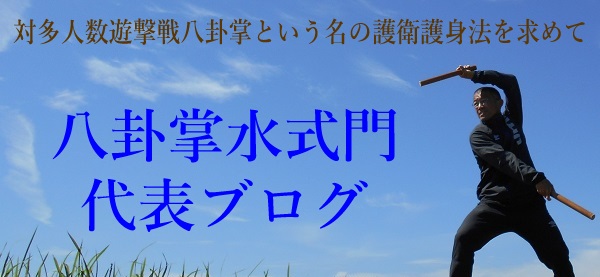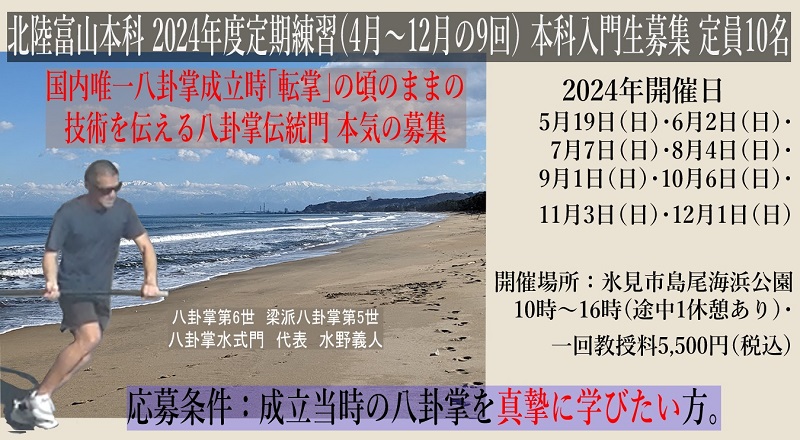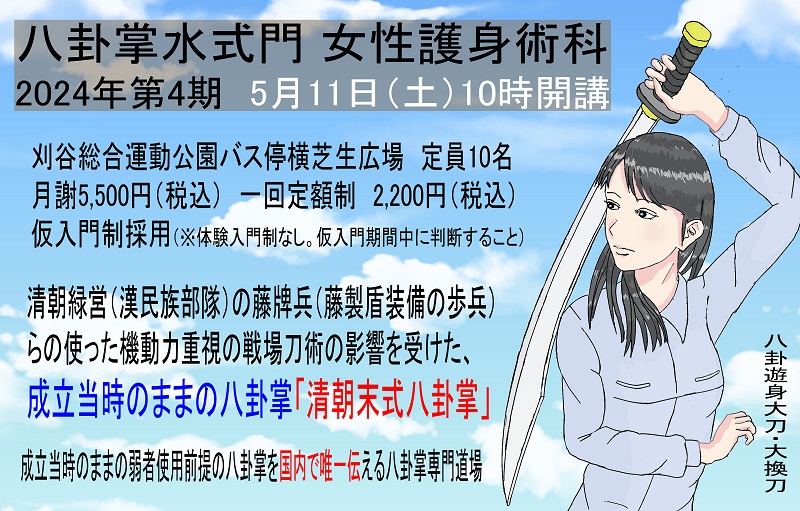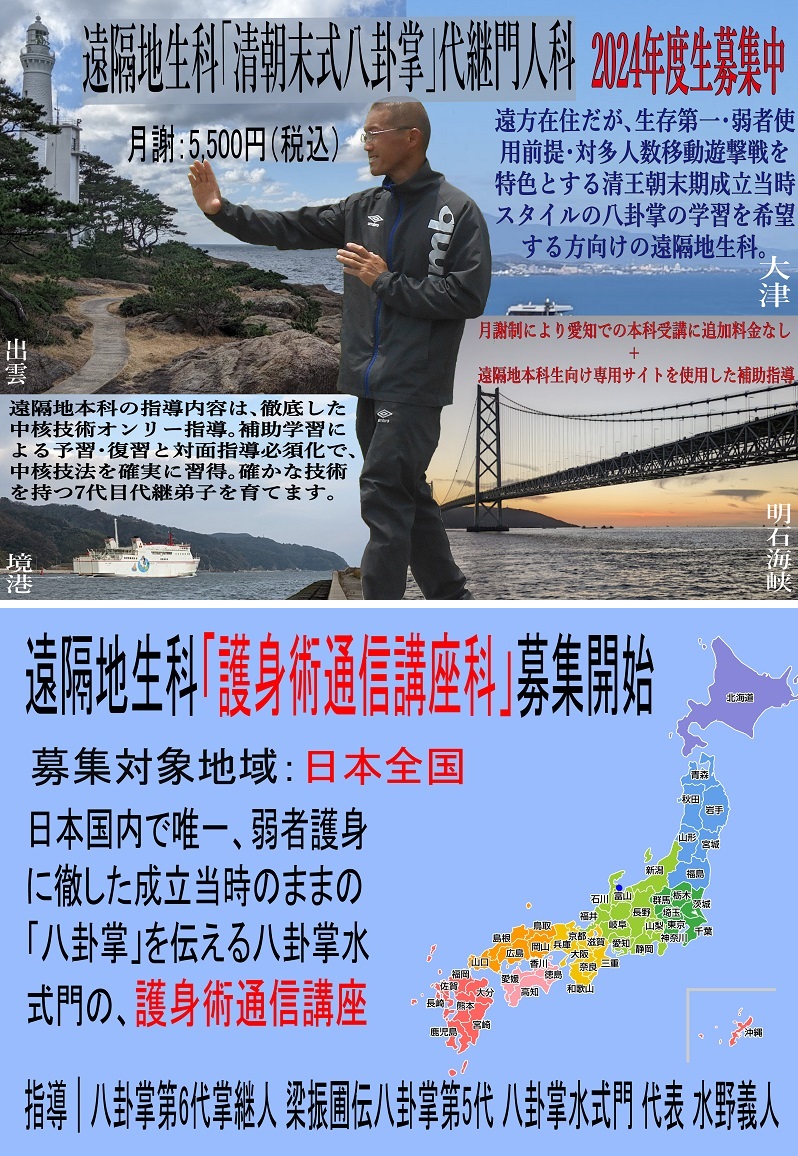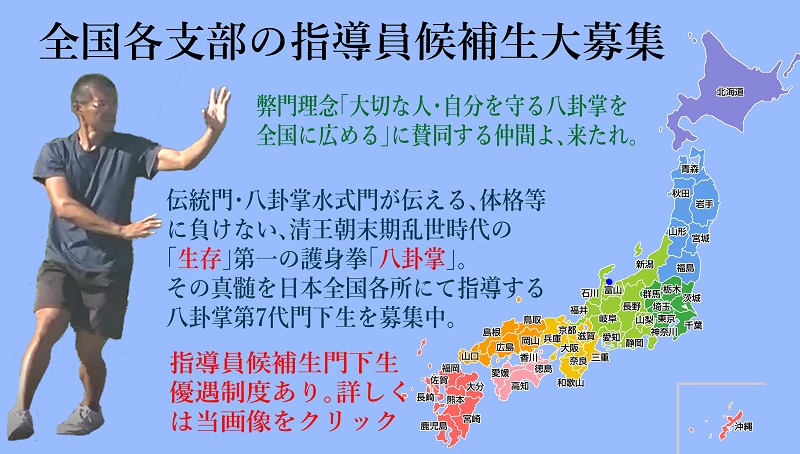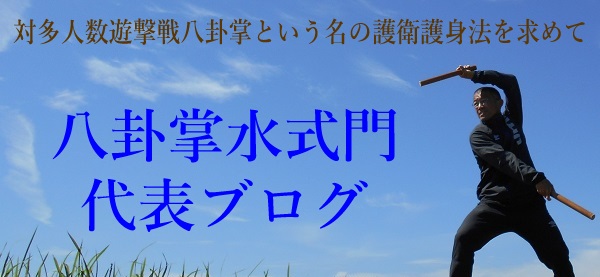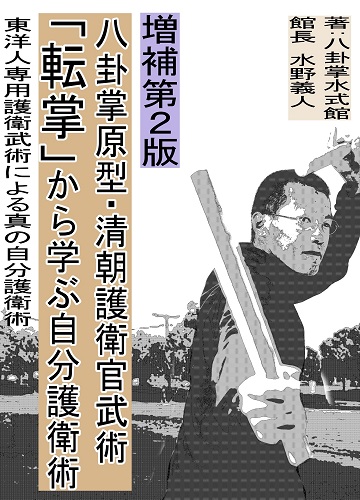服で戦う。よく時代劇で、布や手拭いで対抗するシーンがある。
確かインドネシア辺りでは、布で戦う武術もあるようだ。あれがしばらく、どうしても実行できなかった。モノで戦うことの最後の砦が、服で戦うことだった。
しかしそれも、転掌をマスターしたら実行できるようになった。奥が深く、その方法を悟ってからすでに10年以上が過ぎているが、いまだに上達の余地がある。楽しみである。
さて、どのように戦えばよいのか、どのようにすれば、服でも戦うことができるようになるのか。それは、身体の移動に追随させることである。身体の移動の後を、ついて来させるのである。
服が先行しては、うまく扱うことが出来ない。コシやハリが当然のごとく、全く無いからである。前方向への攻撃を、全くできないわけではないが、服を使っての突き技は、コシ・ハリの無さから有効ではない。サッと出して敵の顔にかぶせてしまうなどは、有効ではあるが。
転掌では、その練習をすでにしていた。答えはすでに、37年前に、楊師より教えてもらっていたのだ。考えてみれば、楊師は、作業着っぽい上着で、何度も何度も刀術を指導してくださった。あれは実は大きなヒントだったのだ。
その時、最も多く見た技は、服を持っての翻身拍打→上翻サイ刀→服を持っての翻身拍打→按刀、であった。翻身拍打で、外方向斜め後ろから迫る敵にけん制の斬撃をし、その服を背負い投げのように背負いながら上斬し、すかさず持ち替え再び前敵に翻身拍打による斬撃、そして離脱しながら按刀、である。
2番目の翻身拍打による斬は、前敵に対するものであるが、移動を止めないことによって服自体に慣性がかかっているため、振り回す服に芯が入り勢いを保ちながら斬撃できるのである。これは、200センチ程度の長い棒を振りまわす遊身大刀の術理に同じである。
自分は、そこまで考えていなかった。言い換えるならば、その動きの中に、転掌の術理を見い出すことができなかった。その時すでに、楊師より数年マンツーマンで習っていたはずだったが、分からなかった。ただ、楊師の服のチャック部分が当たるのが怖くて、半分聞いてなかったのかもしれない。でもそれは言い訳。やはりまだ、転掌について、何もわかっていなかったのだ。
先ほどの技の例を読んで、ある程度水式館で習った人間ならわかるであろう。そうである。服の扱い方を有効にするヒントは、「刀裏背走理」なのである。刀裏背走理を用いるとは、どういうことか。
つまり服を、身体移動で引っ張る、背負う感じで大きく振り回すことだ。その振り回した服が、敵の手に絡めば、十分相手を引っ張り崩す力となる。先ほど言った、振り回す服に帯びた遠心力が、服についているチャックを、凶器に変えることもある。
刀裏背走理による術理で服の武器化を維持するためには、とにかく自分が止まらないことが重要だ。止まらないことで、服自身が、自分と一緒についてきてくれる。出した手(服)の方向の、反対側へ、例えば揺身法を用いて身体を移動させ、伸びきった服を、自分で背負いながら移動していく。追随する服には、移動による慣性の力が宿り、重さを増し、それが敵の手や身体に絡んだりすると、武器を落としたり、敵の態勢を崩したり、敵の眼をくらますことにつながる。
上翻サイ刀によって服を背負うようにして前に進んでいく動きは、楊家連身藤牌における「甲下走牌(こうげそうはい)」に似ている。連身藤牌には、自分の外側に迫った敵に、藤牌を手刀のように出し、反対側へ揺身法で急速移動しながら藤牌を背負って、転身しながら反対側もしくは襲ってきた敵に小旋回して再び振り下ろす、という用法を持った「甲下走牌」がある。この動きが、服を使った戦いのヒントになった。
そのことを思い出し、今朝、暗闇の大和町広場で、黙々と連身藤牌を練習していた。子供たちにもそのことを教えたら、「そんなのわかっていたよ」とのこと。考えてみれば、服で戦う技術に関しては、この子たちはかなり早くからできるようになっていた。一番弟子でもあるこの子は、目的をもって制服で練習していたが、その時来ていた学校のコートを、走りながら脱いで振り回す練習をしていた。学校指定の高額コートゆえ、面食らったものだったが、そのような試みが、彼女に術理の気づきを与えたのかもしれない。
刀裏背走理を学習したことがある門弟の方は、是非とも自分の着ている服で試してみるといい。刀裏背走理の実用性の高さを実感できるはずである。どうせなら、緒戦では着たままにして、移動しながら脱いでそのまま振り回す、などもやってみるとよい。
昔日の転掌では、宦官や宮女は武器を表立って携帯することを許されていなかったため、移動しながら引き出す練習をしていた。それはウーマン・ライト・ガードでも必ず練習してもらう。身分の高い女官は、頭に忍ばせてある丈夫なかんざしを有事にすぐ引き抜き、双匕首のようにして使ったとのことである。ほとんど暗殺技である。
身体移動で引っ張って、その去り打ちの軌道で、前に突出してきた敵の身体部位を、出会いがしらに斬る。服にも使うことができる、その戦闘法に気づいていた草創期の門弟らは、大したものである。
特殊警棒を持つことができないことについて、マイナスの反応をする警備員もいる。しかし、日本のサムライのように、腰に差してすぐに引き抜くことができる状態で携帯してない限り、警棒について有効性は?だと思っている。
私が以前勤めていた、野生動物が最大の脅威であった勤務地では、特殊警棒よりも、常に手に持っているシャッターフック棒の方が頼りだった。シャッターフック棒は120センチの樫材によるものを使用していた。そしてそれと同じ長さの樫材棒で、日頃から練習をしていた。
このようにすれば、引き出す手間がかからない。最も危険な襲撃の際は、3メートル以上あった距離を、わずか2秒で詰められ、身体を入れて流し払い逃げをし続けることだけしかできなかった。特殊警棒で対応していたら、引き抜くことすらできなかったであろう。
実戦的とは、こういうことである。組手で顔面ありを行っていることが、その道場の実戦性を必ずしも示しているのではない。リアルな戦いの現実を知り、「その時」が来たとき、練習でつちかった動きを実行するために、事前準備をするか、である。
だから転掌には、槍術に、扎のような、滑らせる技法がないのである。そこらにある棒の表面は凸凹で傷だらけ、手袋でもつけてない限り、あの技法は実行できない。転掌に伝わる双身槍が持ち替える技術ばかりなのは、そのためである。ここまで想定して、「実戦的」だと宣言できる。
服で戦うことは、棒など持ち歩くことができない人に、大きな希望となる。服ならば、高い確率で持っている(着ている)し、いつでも携帯し得る武器?となるだろう。
一番弟子は、万が一の時制服の上着を脱いで振り回すため(セーラー服だったので、ブレザー制服のような上着がなかった)に、下にかならずTシャツを着ていた。そこまで考えていた。彼女の発想は、警備や警察の仕事に就いている人間に大きなヒントをもたらすだろう。そこまで考えて職務に臨んでいる職員がどれだけいるだろうか。
警察官には、やはりどうして特権意識が見え隠れする。そして武術を学ぶことに懐疑的である。「おまわりさんもどうですか、柔道をやっていたのは、もうかなり昔のことでしょう?」と言っても、「何を言っているか、いまさら」程度の反応を何度もされた。
警察官も転掌を学ぶとよい。柔道技で足を引っかけ、倒して制圧するだけが「取り押さえる」のではないのだ。警察官は、持っている拳銃と国家権力(公務執行妨害による現行犯逮捕や緊急逮捕権限)により、すでに一般人を大きくしのぐ強みがある。あとは攻撃を受けないための身法だけである。彼らこそ、「当たらないこと・斬られないこと」に注意を払わなければならない。
有事の際、一般人をまもるのはあなたたちなのだから。最後の砦なのだから。警察学校で学んだ時の身体で戦うことはできない。今その時の身体で対処するしかないのである。であるならば、今この瞬間に、その身体に、身をかわし、持ち得る道具で対処しうる身法を身につけようではないか。
真に身を守る技術とは、護身グッズを扱う技術ではない。身体を即座に動かし間をとり、逃げる余裕、けん制攻撃をする余裕、護身グッズを使う余裕、身の周りのものを使う余裕を生み出す技術である。それには、移動技術が必要である。移動技術は、転掌などの、昔日の武術で学ぶことができる。